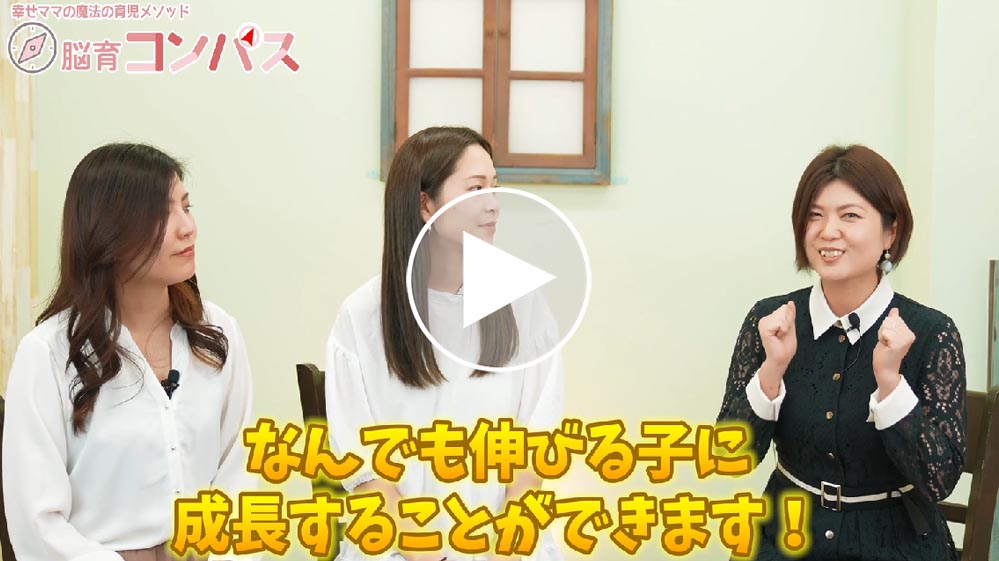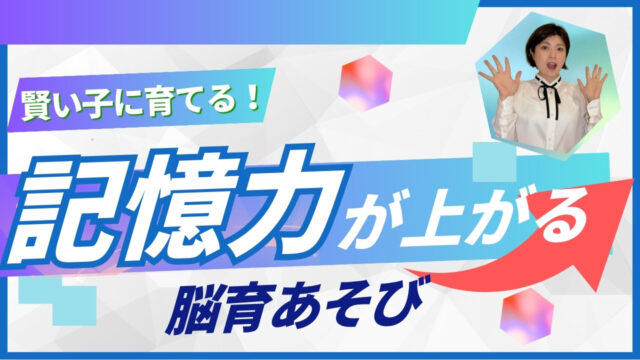おもちゃの取り合い・順番待ちができない子どもたち…脳の発達から考える対応法
こんにちは、脳育コンパス主宰のおかみつるです。
「またおもちゃの取り合いで喧嘩が…」
「いつになったら順番を待てるようになるの?」
と、お子さんの姿に心を痛めているママやパパは多いのではないでしょうか。
特に兄弟がいるご家庭や、保育園に通い始めたお子さんのいるご家庭では日常的な悩みかもしれません。
今日は、脳科学の視点からこの問題を紐解き、具体的な対応法をお伝えしていきます。
目次
おもちゃの取り合いは脳の発達の自然なプロセス
まず最初に知っておいていただきたいのは、おもちゃの取り合いや順番待ちができないのは、子どもの発達の自然なプロセスだということです。
親としては「なぜ貸してあげないの?」「仲良く遊んでよ」と言いたくなる気持ちはよくわかります。
しかし、この「モメゴト」は実は子どもにとって、自分の気持ちを整理したり、社会性を学んだりするための貴重なチャンスなのです。
なぜ取り合いが起こるの?脳の発達から考える
子どもたちがおもちゃを取り合ったり、順番を待てなかったりするのには脳の発達段階が関係しています。
特に前頭葉(感情コントロールや目標設定、判断を担当)と側頭葉(言語理解や長期記憶に関わる)の発達が鍵となります。
幼い子どもたちは、まだ自分の気持ちにすら気づいていない段階です。
「自分が何を感じているのか」を認識し、それを言葉にして表現することは、大人が思っている以上に難しい作業なのです。
月齢・年齢別の特徴と対応法
1歳~3歳の子どもの場合
- 「これは自分のもの」という意識が強くなる時期
- 共同で遊んでいるように見えても、実は「並行遊び」の段階
- 言葉でのやり取りがまだ難しく、行動(手が出る、噛む)で表現しがち
- 順番や「貸す・借りる」という概念がまだ根付いていない
- 気持ちを代弁する
「今〇〇ちゃん、これで遊んでいるね。楽しそうだね。」
「△△くんも、これ使いたいよね。やってみたいよね。」 - テリトリーを分ける
「このマットの上は〇〇ちゃんのスペース、こっちのテーブルは△△くんのスペース」と分けておく - 「貸してあげなさい」と強制しない
代わりに「いいよ、ちょっと待ってね。今使ったら後で貸してあげるね」という言葉を教える - 感情の動きを尊重する
貸すことイコール「いい子」ではなく、自分の気持ちを大切にしながら相手にも配慮することを学ぶ時期と捉える
年齢差がある兄弟姉妹の場合(例:5歳と1歳)
- 上の子はルールを理解できる段階だが、常に我慢を強いられることが多い
- 下の子は「すべて自分のもの」という認識で、区別なく触りたがる
- 上の子が「絶対に貸さない」と頑なになりがち
- 上の子の気持ちに寄り添う
まずは上の子の気持ちから優先的に配慮し、その不満や思いを受け止める - 事前のルール作り
「このおもちゃは絶対に貸さなくていい」「こっちは一緒に使ってもOK」など、上の子と話し合ってルールを決める - 上の子のテリトリーを守る
下の子が触れないよう高い場所に置くなど、約束したことは親も一緒に守る環境を整える - 感謝の気持ちを伝える
上の子が譲ってくれた時は「ありがとう」と感謝を伝える(ただし、無理に「いい子」を演じさせない)
トラブルを防ぐための工夫
1. 事前のルール作り
特に4歳以上の子どもには、落ち着いているときに事前にルールを決めておくことが効果的です。
- テレビの場合:「今日はお姉ちゃんが先、明日は弟くんが先」など交代制にする
- 時間制限:「10分使ったら交代」というルールを砂時計などで視覚化する
- 共通の目標:「1週間このルールを守れたら、週末に一緒に映画を見に行こう」など
2. 物理的な環境調整
- 危険なおもちゃや特に大切なものは、届かない場所に置く
- 十分な数のおもちゃを用意し、似たようなものを複数持たせる
- 遊ぶスペースを区切る(テントやマットで領域を明確に)
3. 大人の関与のバランス
兄弟喧嘩において、親がいつも間に入ってジャッジしていると、「親がどちらの見方をするか」を試すために喧嘩が始まることもあります。
意外にも、親が近くにいない方が早く解決することも。
- 基本は見守る姿勢を大切に
- 危険な状況(叩く、噛むなど)では即座に介入
- 介入する場合も、どちらが「正しい」かを決めるのではなく、互いの気持ちに寄り添う
大切なのは「育ちのチャンス」と捉えること
おもちゃの取り合いや順番待ちの喧嘩はストレスに感じがちですが、これを「脳の発達のチャンス」と捉え直してみませんか?
お子さんが自分の気持ちに気づき、相手の気持ちを想像し、言葉で表現する能力を身につける貴重な機会なのです。
まさに「レベルアップ」の瞬間と考えれば、少し余裕を持って見守ることができるかもしれません。
そして、この「取り合い」の経験を通して育まれる力は、将来の人間関係の基礎になるものです。
今は大変でも、長い目で見れば大切な「社会性の練習」なのです。
親としては、完璧な対応を目指すのではなく、お子さんの成長に寄り添い、時にはうまくいかなくても、一緒に学び続ける姿勢が大切です。
あなたのお子さんに最適な脳の発達を促すために
脳育コンパスでは、子どもの脳の発達段階に合わせた関わり方をお伝えしています。
おもちゃの取り合いや順番待ちの問題も、脳の発達という視点から見ると、対応の糸口が見えてきます。
子育てで悩んだとき、「なぜこの行動が起きるのか」を脳科学の視点から理解できると、イライラが減り、適切な関わり方が見えてきます。
お子さんの「困った行動」の裏にある脳の発達メカニズムを知りたい方、感情コントロールの力を育てる具体的な関わり方を学びたい方には、ぜひ脳育コンパスのオンラインベーシックセミナーをお勧めします。
オンラインベーシックセミナーのご案内
「なぜうちの子は言うことを聞かないの?」
「どうしたら感情的にならずに子どもと向き合えるの?」
「兄弟喧嘩にイライラしない方法が知りたい…」
脳育コンパスのオンラインベーシックセミナーでは、子どもの脳の発達段階に合わせた関わり方を、科学的根拠に基づいてわかりやすくお伝えします。
今回のテーマである「おもちゃの取り合い・順番待ち」はもちろん、子どもの自立心や自己肯定感を育てる声かけ、感情をコントロールできる子に育てるための関わり方など、日常の子育てがグッと楽になる具体的な方法を学べます。
セミナーに参加された方からは
「子どもの行動の理由がわかって気持ちが楽になった」
「具体的な声かけを知れて実践できている」
「兄弟喧嘩が減った!」
など、喜びの声をたくさんいただいています。
この機会に、子育ての悩みを「脳育」の視点で解決する第一歩を踏み出してみませんか?
あなたとお子さんの笑顔あふれる日々を心から応援しています。