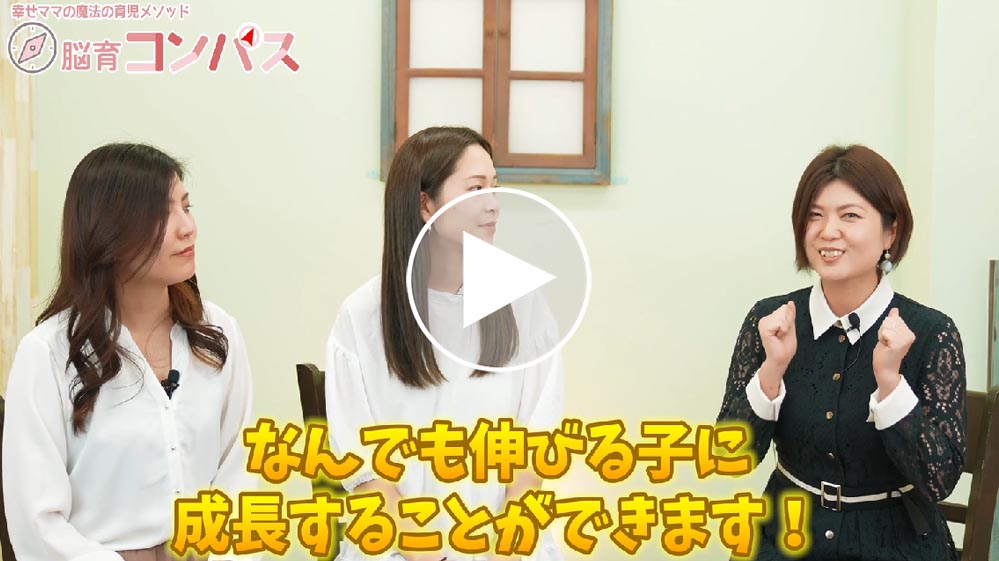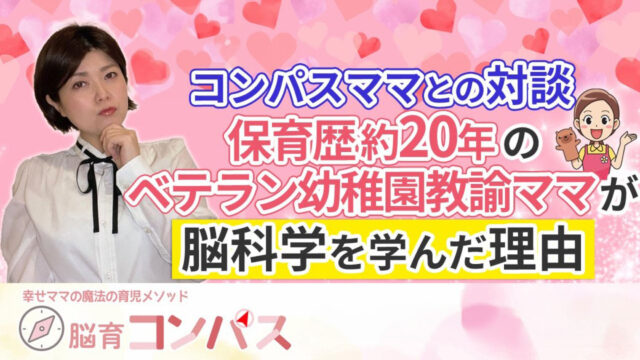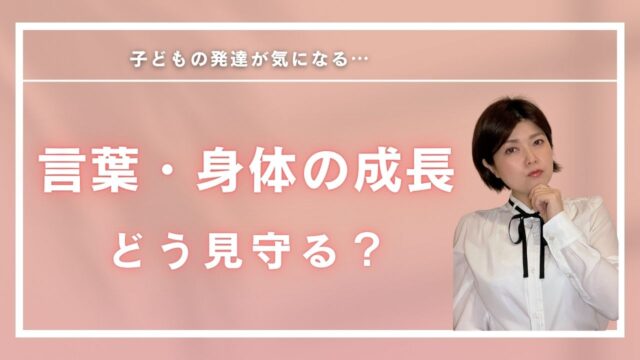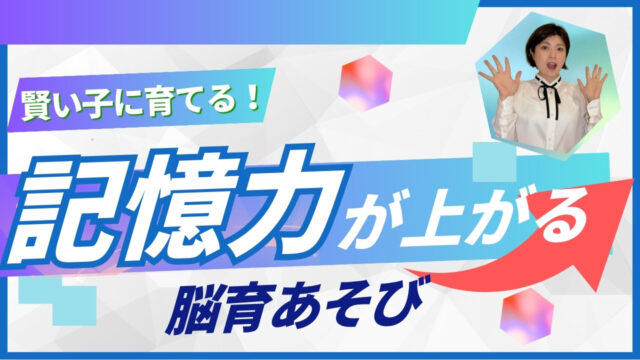【小学校受験対策】脳育コンパスが育てる「合格脳」~知識より大切な0〜3歳の土台づくり~
- 小学校受験で実際に出題される問題とその対策法
- 脳育コンパスが小学校受験にどう役立つのか
- 0〜3歳から始める効果的なお受験準備のステップ
- 実際に小学校受験・中学受験に合格した子どもの育て方
こんにちは、脳育コンパス主宰のおかみつるです。
春になると、お子さまの教育や将来について考える時期ですね。特に小学校受験を視野に入れているお母さまは、「どんな準備をすればいいのだろう」「うちの子に合った対策は何だろう」と悩まれているのではないでしょうか。
今日は、なぜ脳育コンパスがお受験対策に効果的なのか、そして早期からの脳の土台づくりがどれほど重要かについて、実際の受験問題や我が子の受験体験を交えながらお話ししたいと思います。
目次
小学校受験の真実:求められるのは「知識」ではなく「脳の力」
小学校受験というと、「漢字をたくさん覚えさせないと」「計算問題を早くから練習させないと」と考えがちです。
しかし、実際の小学校受験ではそういった早期学習や知識の詰め込みは求められていません。
実際の小学校受験問題の例
実際に出題されるのは、こんな問題です。
- 空間認知力を問う問題:積み木が動物から見るとどう見えるか
- 論理的思考力を問う問題:折り紙を折って切った時に生まれる形
- 規則性の理解:赤・青・黄色の繰り返しパターンの続きを予測する
- 記憶力・理解力:長文の聴き取り問題
- 指示理解と実行力:複数の手順を覚えて行動する課題
これらは単なる知識ではなく、「見る力」「考える力」「記憶する力」「空間を認識する力」など、脳の基本的な機能を評価するものです。
つまり、小学校受験で本当に問われているのは「知識」ではなく「脳の土台」なのです。
私自身の子育てと受験成功体験
脳育との出会いが変えた息子の未来
脳育コンパスを始めるきっかけとなったのは、我が家の息子でした。
彼が小さい頃は特性が強く、フリースクールも視野に入れていた時期があり、お受験は全く考えていませんでした。
しかし、脳科学に基づいた関わりを始めてから、息子は少しずつ変化していきました。
集中力や物事に向き合う力が育ち、その結果、年長の夏頃に本人から「受験したい」という言葉が出てきたのです。
息子は見事に小学校受験に合格して私立小学校に通い、そして今年、中学受験も希望校に合格しました。
脳育コンパスがなければ、この二度の合格はなかったと確信しています。
長女の受験経験からの学び
長女も受験を経験したのですが、私が脳科学を育児に活用し始めたのは長女が6〜7歳の頃、息子が4〜5歳の頃でした。もっと早くに出会っていれば、より効果的だったと実感しています。
それでも、脳科学的アプローチは子どもたちの受験準備に大きく貢献しました。
実際の受験テストから見える「必要な力」
子どもの観察力と空間認知力を試す課題
息子の受験では、空中に斜めに浮いたサイコロを観察して画用紙に描くという課題がありました。
親への面接中、子どもはこの課題に取り組みます。空間認知力と描写力の両方が試されるテストです。
集中力と手先の器用さを見る課題
長女の受験では、「待ち時間に折り鶴を折って待っていてください」という指示がありました。
これは単に折り紙の技術だけでなく、集中力や時間の使い方も見られていたようです。
こうした経験から、小学校受験では「知識」よりも「脳の働き」が重視されていることを実感しました。そして脳育コンパスで育てている力こそが、まさに受験で問われる力なのです。
脳育コンパスで伸びる4つの「お受験必須能力」
脳育コンパスでは、0歳から3歳の時期に「遊び」を通じて脳の土台を作ることを大切にしています。この時期に育まれる能力が、後のお受験でも大きな力となります。
1. 空間認知力:図形や立体を理解する力
積み木遊びやパズル、はめ込み遊びなどを通して、形や空間を認識する力を育てます。
これは小学校受験で必ず出題される「積み木の模写」や「図形の構成」に直結します。
3歳頃には、簡単な形を見て記憶し、同じものを作る練習もします。
この力は、テストでの図形問題や立体の見え方問題に大きく役立ちます。
2. 記憶力・ワーキングメモリー:指示を理解し実行する力
フラッシュカードや絵カードクイズ、音やリズムを覚える遊びを通して、記憶力を鍛えます。
小学校受験では「指示行動」や「長文聴き取り」など、複数の情報を覚えておく必要がある問題が多く出題されます。
例えば「体育座りをして、線の向こうまでケンケンで行き、箱から赤い折り紙を取って丸め、青い箱に入れる」など、5つの指示を一度に覚える必要があります。
脳育コンパスで育った記憶力がここで活きてきます。
3. 想像力と協調性:自由遊びでの振る舞い
自由遊びの中で、ルールを守りながら想像力を発揮する力を育てます。
小学校受験のテストでは、「自由遊び」の時間に、お子さまがどれだけルールを守り、想像力豊かに遊べるかも見られています。
例えば、魅力的なおもちゃがたくさんある中で「この枠から出ないで遊んでね」「このおもちゃは壊れているから触らないでね」といったルールをどれだけ守れるか、また他の子と協調して遊べるかが評価されます。
4. 手の巧緻性:工作や描画の基礎となる力
手を使った様々な遊びを通して、手先の器用さを育てます。
小学校受験では工作や折り紙、お絵描きなどの課題もあり、ここでも脳育コンパスの効果が発揮されます。
0歳0ヶ月から始める「手の発達」に合わせた遊びが、後の工作テストの土台になります。
実践者の声:脳育コンパスで小学校受験に合格
実際に、脳育コンパスのメソッドを実践されていたインストラクターのお子さまが小学校受験に見事合格されました。
その方からは「脳育コンパスをやっていて本当に良かった」「受験対策のプリントに進んだ時に、すごくやりやすかった」というお声をいただいています。
もちろん、私自身の経験からも断言できます。
脳育コンパスをやっていなかったら、息子の小学校受験も中学受験も合格はなかったでしょう。
お受験成功への3ステップ
お受験対策として効果的な流れは以下の3ステップです。
ステップ1:0〜3歳で脳の土台づくり
遊びを通して、空間認知・記憶力・想像力・手の巧緻性などを育てる時期です。
この時期の良質な体験が、後のテスト問題理解の基盤になります。
ステップ2:4〜5歳で体験を紙に置き換える練習
体験型で培ってきた能力を、ペーパーテストで発揮できるよう練習する時期です。
「見たことがある」「体験したことがある」ことが、問題理解の助けになります。
ステップ3:受験直前に受験特有のインプット
受験に必要な基礎知識や解答テクニックを学ぶ時期です。
この段階で初めて「受験対策」らしいことを行います。
重要なのは、この順番です。
体験なしにいきなりペーパー学習を始めても、お子さまは理解することができません。紙の上での問題が「何を聞かれているのか」を想像できないからです。
一方、脳育コンパスで脳の土台ができていると、「紙の上での表現」への移行がスムーズになります。「見たものを頭の中でイメージして再現する力」が育っているからです。
今すぐできる!お受験準備のための脳育コンパス
現在、脳育コンパスのオンラインベーシックセミナーを開催しています。
幼児教室よりもコスパが良い理由
お受験を考えているご家庭にとって、このセミナーは単なる「教育法」の学びではなく、お子さまの将来の可能性を広げる投資となるでしょう。
通常の幼児教室は週1回1時間程度で月額2〜3万円。それに対し、脳育コンパスを実践すれば
- 朝15分・夜15分の毎日の関わりで、週に約3.5倍もの学びの時間を確保
- わざわざ外出する必要もなく、日常生活の中で実践可能
- 子どもの機嫌や体調に左右されず、最適なタイミングで実践できる
例えば私は、当時フルタイムの会社員として勤務していましたので、毎日の関わりは朝15分・夜15分程度でしたが、それでも小学校受験に成功しました。
特に、生まれたときから取り組んでいた次女は、本格的な受験対策をたった3ヶ月やっただけで合格してしまいました。
お申し込みはお早めに!
人間の脳は3歳までに80%できあがることが、研究で明らかになっています。
つまり、脳は毎日すごいスピードで変化しています。
早ければ早いほど効果をもたらすことは間違いありません。
お子さまの可能性を最大限に引き出す脳育コンパスで、お受験対策の第一歩を踏み出しましょう。
まとめ:脳育コンパスで育てる「合格脳」
小学校受験は知識の詰め込みではなく、脳の土台が問われる試験です。
0〜3歳の時期に脳育コンパスで適切な刺激と経験を与えることで、お子さまの脳の土台をしっかり築くことができます。
私自身の子育て経験からも、脳育コンパス受講生の経験からも、脳育コンパスが小学校受験、そして中学受験にも効果的だったことを実感しています。
早期からの取り組みで、お子さまの将来の可能性を広げていきましょう!